ストラトキャスターを弾いてみたい、でも「どのモデルがいいのか?」「どんなアーティストが使っているのか?」と迷ってしまう…。そんな悩みを抱える方は少なくありません。
ギター選びは音楽スタイルや好みに大きく関わるからこそ、参考にすべきは“実際にストラトキャスターを使用しているアーティスト”たちです。
この記事では、ジャンル別に有名ギタリストの使用例を取り上げつつ、その音作りや機材の特徴、初心者にもわかりやすい選び方のヒントまで詳しく解説しています。
信頼性のある情報と、ギタリスト目線での分析を通して、あなたにぴったりの一本が見えてくるはずです。きっとこの記事がお役に立つと思いますので、ぜひ最後までお読みください。
出典:フェンダー公式
- ストラトキャスターを使用している代表的なアーティストとそのプレイスタイル
- モデルごとの音の違いや特徴、各アーティストの使用機材
- ストラトキャスターが活躍する音楽ジャンルとその理由
- 初心者に向いたストラトキャスターの選び方とおすすめモデル
ストラトキャスターを使用しているアーティストとそのプレイスタイル
ストラトキャスターは、音楽史に名を刻む多くのギタリストたちによって磨かれてきたギターです。そのサウンドの多様性や演奏性の高さは、アーティストごとに異なる表現を可能にし、それぞれのスタイルに深く根付いています。
この章では、ジャンルや世代を問わずストラトを愛用してきたアーティストたちに焦点を当て、そのプレイスタイルや音作りとの関係性を解説します。初心者でも理解しやすいよう、代表的なプレイヤーの特徴や音の傾向に注目しながら見ていきましょう。

エリッククラプトンとストラトキャスターの魅力
エリック・クラプトンは、ストラトキャスターを語るうえで欠かせない存在です。彼のプレイスタイルとサウンドは、ギターそのものの魅力と直結しており、初心者からプロまで幅広い層に影響を与えています。ここでは、クラプトンがなぜストラトキャスターを愛用し続けるのか、その理由を掘り下げていきます。
ストラトとクラプトンの関係性
- 「ブラッキー」との関係
クラプトンが最も愛用したギター「ブラッキー」は、複数のヴィンテージストラトを組み合わせて作られた特注モデルです。 - スムーズで粘りのあるトーン
クラプトンのソロで聴ける滑らかで粘りのある音色は、ストラトキャスターのシングルコイルピックアップならではの特徴です。 - コントロール性能の高さ
演奏中にボリュームやトーンを繊細に調整するクラプトンのスタイルは、ストラトの操作性と相性抜群です。
なぜ多くの人が惹かれるのか
- オーセンティックなブルースサウンド
クラプトンのプレイは、ストラトを通じてブルースの原点に立ち返らせてくれます。 - 親しみやすい音の幅
強く歪ませずとも深みのあるサウンドが出せるため、初心者にも扱いやすいのが魅力です。 - 手に入れやすいシグネイチャーモデル
クラプトンモデルは現行で販売されており、サウンドの再現が現実的です。
クラプトンはストラトキャスターを通じて、シンプルながらも深い音楽を世界に届けてきました。その姿は、ギターを選ぶ基準を持たない初心者にとっても、ひとつの「理想形」となり得ます。

イングヴェイモデルの特徴と魅力
ネオクラシカル・メタルの開拓者として知られるイングヴェイ・マルムスティーンは、ストラトキャスターを自らの「剣」として使いこなすギタリストです。ここでは、彼のシグネイチャーモデルが持つ特徴と、その魅力について紹介します。
イングヴェイモデルの主要な特徴
- スキャロップド指板
フレットの間が彫り込まれていることで、軽い力で弦を押さえやすくなり、ビブラートやチョーキングが繊細に表現できます。 - セラミック製YJMピックアップ
高出力でクリアな音質を実現しており、速弾きでも粒立ちが良いサウンドが得られます。 - ブラスナットと22フレット構成
高域のサスティンと音の明瞭さを確保する設計になっています。
なぜイングヴェイモデルが支持されるのか
- 高速プレイを前提にした構造
ピックアップや指板など、全体がスピード重視で設計されているため、テクニカル系ギタリストには理想的です。 - メタル以外にも応用可能
クラシックやジャズ風の旋律にも向いており、幅広いジャンルで個性を発揮できます。 - 独自性の強いスタイルに憧れる層に人気
唯一無二のサウンドを目指すプレイヤーにとって、イングヴェイモデルは強力な選択肢になります。
イングヴェイモデルは、技術志向のギタリストにとって憧れの的であり、演奏をより自由に、表現力豊かにしてくれる仕様がそろっています。見た目もクラシックかつ派手さがあり、ライブでも映えるギターです。
ジョン・フルシアンテの魅力とプレイスタイル
ジョン・フルシアンテは、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのギタリストとして世界的に知られています。彼のプレイスタイルはテクニックに頼り過ぎない感情的な表現に特徴があり、特にストラトキャスターとの相性が抜群です。ここでは、彼の演奏スタイルや音作りの魅力について掘り下げていきます。
シンプルなのに心に残るプレイ
- 感情を優先したフレージング
難しいフレーズよりも、聴く人の心を動かす音を重視しています。 - コードと単音の絶妙なバランス
アルペジオやリフといった要素を交えながら、メロディの流れを自然につなげます。 - 「間」の取り方が上手い
音を詰め込み過ぎず、あえて空白を活かすことで楽曲に奥行きを与えます。
音作りに対するこだわり
- ヴィンテージのストラトキャスターを使用
古いストラトの独特なサウンドを生かし、温かみのある音を追求しています。 - アナログ機材への強い信頼
デジタルではなくヴィンテージのアンプやエフェクターを使うことで、サウンドに深みを加えています。 - 楽曲に合わせた柔軟なセッティング
必要に応じて歪み具合やトーンを調整し、曲の雰囲気を壊さない演奏を心がけています。
フルシアンテの演奏は一見シンプルですが、感情や空気感を音に乗せる技術が詰まっています。テクニックの派手さに頼らないからこそ、多くのリスナーの心に響くのです。ストラトキャスターの素朴さと表現力の豊かさを活かした彼のプレイは、学ぶべきポイントが非常に多い存在です。
古のレジェンド:ジミヘンドリックス
ジミ・ヘンドリックスは、ストラトキャスターをロックの象徴へと導いた伝説的ギタリストです。彼の登場により、ギターという楽器は単なる伴奏器具から、自己表現の手段へと変貌を遂げました。ここでは、ジミヘンとストラトキャスターの深い関係性について紹介します。
革命的だったプレイスタイル
- 左利き用のギターを右利き用で演奏
本来の設計とは逆に構えたことで、独特の音と演奏感を生み出しました。 - 大胆なフィードバック奏法
アンプからの音のハウリングを操るスタイルは、当時としては衝撃的でした。 - ブルースを基盤としたロックアプローチ
基礎は古典的でも、表現は前衛的で新しい音楽の地平を開きました。
使用ギターと音作りの特徴
- フェンダー・ストラトキャスターを愛用
特に白いモデルが有名で、柔らかくも攻撃的なサウンドを両立していました。 - ワウペダルやファズフェイスを多用
エフェクターを積極的に活用し、音に劇的な変化を加えるのが得意でした。 - ライブでの即興性
毎回違う演奏を見せることで、観客を飽きさせないステージを作り上げていました。
ジミヘンは、ギターの「限界」を自らの手で押し広げた存在です。彼の音楽性とストラトキャスターの相性は極めて高く、その後の多くのギタリストたちに多大な影響を与えました。表現力を最大限に発揮できるギターとして、ストラトキャスターを象徴的な存在へと昇華させた点でも、ジミヘンはまさにレジェンドと呼ぶにふさわしい人物です。

世界のストラトプレイヤーとその音楽性
ストラトキャスターを愛用するギタリストは、世界中に数多く存在します。ここでは、ジミ・ヘンドリックスやクラプトンといった超有名アーティスト以外で、独自の音楽性をストラトで表現している海外のプレイヤーを取り上げます。個性豊かなサウンドの魅力を、ぜひ知っておいてください。
幅広いジャンルで活躍する名プレイヤーたち
- マーク・ノップラー(Dire Straits)
指弾きによる繊細でクリアなトーンが特徴。無駄のない演奏で、メロディアスなロックサウンドを確立しました。 - ジョン・メイヤー
モダンブルースとポップスを融合。甘く深いトーンで、若い世代にもストラトの魅力を広めています。 - ジェフ・ベック(晩年のスタイル)
ピックを使わない指先のタッチや、アーム操作を駆使して浮遊感あるサウンドを追求しました。 - ロリー・ギャラガー
使い込んだストラトで荒々しくも情熱的なブルースを展開。ライブでのエネルギーが圧倒的です。 - バディ・ガイ
ブルース界の重鎮。ビビッドな見た目と鋭いトーンで、聴衆の心を掴んで離しません。
それぞれのギタリストが、ストラトキャスターのポテンシャルを最大限に引き出してきました。ジャンルや奏法によって音の印象が変わるのは、ストラトならではの魅力です。音楽性の広さと柔軟さが、これほどまでに多くのアーティストに愛される理由だといえるでしょう。
日本人の注目プレイヤーの紹介
ストラトキャスターは海外のイメージが強いギターですが、日本でも多くのプレイヤーがその魅力を引き出しています。ここでは、国内で注目されるストラト使いのギタリストを紹介し、彼らの特徴的な音楽性に触れていきます。
日本人ならではのセンスが光るプレイヤー
- Char
日本のロックシーンのパイオニア的存在。独特のグルーヴ感とエッジの効いたトーンが特徴です。 - 山内総一郎(フジファブリック)
繊細さと情熱をあわせ持つ演奏が印象的。バンド全体のサウンドに深みを与える存在です。 - 春畑道哉(TUBE)
情景が浮かぶようなメロディアスなプレイが持ち味。夏を感じるサウンドで多くのファンを魅了しています。 - 岸田繁(くるり)
オルタナティブな楽曲に、ストラトの素朴な響きを巧みに溶け込ませています。 - SUGIZO(LUNA SEA / X JAPAN)
空間系エフェクトを駆使し、幻想的な世界観を構築。ストラトの多面性を感じさせるプレイヤーです。
国内のギタリストたちも、ストラトキャスターを通じて幅広い音楽表現に挑戦しています。海外アーティストと同様に、それぞれが自分だけの音を追求しており、ギター初心者にとっても大きな刺激となる存在です。身近なアーティストを通じてストラトの魅力を感じることで、よりリアルな参考になるはずです。
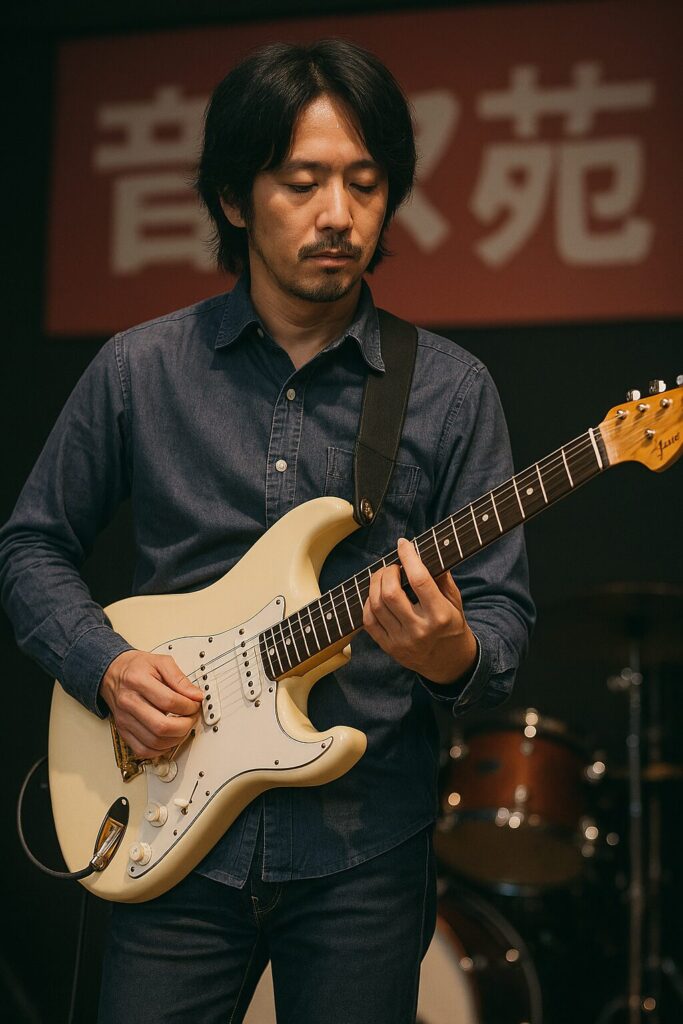
パンクシーンでの使われ方
ストラトキャスターは、パンクロックの世界でも多くのギタリストに選ばれてきました。荒削りなサウンドとシンプルな構造が、パンクシーンにフィットしているのです。ここでは、パンクにおけるストラトの役割と使われ方を解説します。
ストラトキャスターがパンクに好まれる理由
- 軽量で取り回しが良い
ライブで動き回るパンクギタリストにとって、軽いボディは大きなメリットです。 - 構造がシンプルで壊れにくい
過酷なライブ環境にも耐えやすく、修理や改造が容易です。 - シングルコイルのジャリッとした音がパンク向き
鋭く荒々しいサウンドが、疾走感ある演奏と相性抜群です。 - 安価なモデルも多く入手しやすい
初心者や若いバンドマンでも手が届く価格帯が多く、導入の敷居が低いです。
代表的な使用例
- ジョニー・サンダース(New York Dolls)
- ジョー・ストラマー(The Clash)※テレキャス主体だがストラトも使用
- ビリー・ジョー・アームストロング(Green Day)※初期にストラト系を使用
パンクはテクニックよりも勢いやメッセージ性が重視されるジャンルです。ストラトキャスターはそのラフで直接的な音の出方が、パンクのエネルギーと見事にマッチしています。安定性・入手性・サウンドの三拍子が揃ったギターとして、多くのパンクスに支持されてきました。
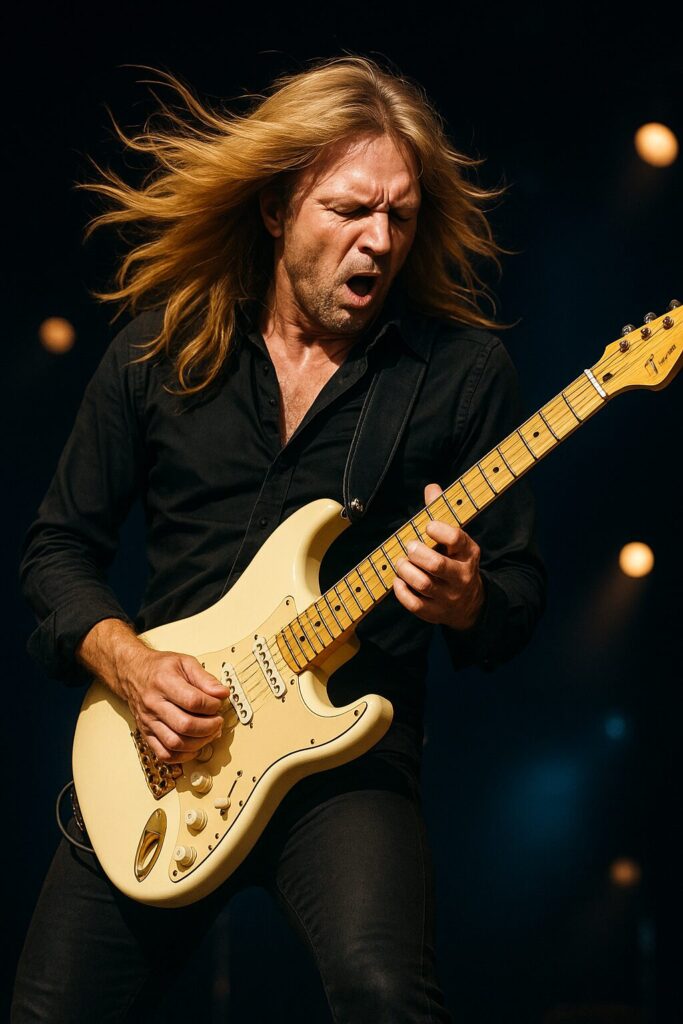
メタルやハードロックとの相性は?
ストラトキャスターは一見、メタルやハードロックには不向きに思われがちですが、実際には数多くの名ギタリストがストラトで重厚なサウンドを作り出しています。ここでは、その理由や活用方法を紹介します。
メタル/ハードロックでも選ばれるポイント
- ピックアップをハムバッカーに交換できる
太くてノイズの少ない出力が得られるため、ストラトでも十分にヘヴィな音が作れます。 - ブリッジのフローティング構造が多彩なアーミングに対応
スティーブ・ヴァイやイングヴェイのような表現力豊かなソロに最適です。 - ネックの握りやすさと弾きやすさが速弾き向き
スムーズな運指を可能にし、メタル系の難易度の高いプレイにも対応できます。 - 音の分離が良くコードの輪郭が出やすい
歪ませても音が潰れにくいため、テクニカルなプレイが映えます。
使用例のある代表的プレイヤー
- イングヴェイ・マルムスティーン
- リッチー・ブラックモア(元Deep Purple)
- ジェイク・E・リー(元Ozzy Osbourne)
- エイドリアン・スミス(Iron Maiden)※一部ストラト仕様モデルを使用
ストラトキャスターはカスタマイズの自由度が高く、ジャンルを超えたサウンドづくりに適しています。ピックアップやブリッジの調整次第で、メタルやハードロックに必要な音圧とキレを十分に再現可能です。音の立ち上がりの速さと操作性を活かせば、激しいジャンルにも柔軟に対応できる一本です。

ストラトキャスターを使用しているアーティストとそのプレイスタイルの総括
ストラトキャスターを使用するアーティストたちは、それぞれ異なるサウンド志向や演奏スタイルを持ちながらも、共通してこのギターの表現力の高さに惹かれています。
ブルースの巨匠からモダンなロックプレイヤーまで、幅広いジャンルで活躍する彼らのプレイには、ストラトならではの個性が強く反映されています。
構造の柔軟性と音色の奥深さが、多くのアーティストに選ばれ続ける理由と言えるでしょう。これからストラトキャスターを選ぶ人にとっても、参考になるヒントが多く詰まっています。
どんなジャンルのアーティストが使用している?ストラトに最適な音楽は?
ストラトキャスターは多彩な音色を生み出せるギターとして知られています。では、その中でも特にどんな音楽ジャンルで力を発揮するのでしょうか。ここでは、ストラトが特に向いている音楽ジャンルとその理由について解説します。

ストラトが得意とする音楽ジャンル
- ブルースとの相性が抜群
シングルコイルの繊細なレスポンスが、表情豊かな演奏に最適です。 - ファンクやR&Bでも大活躍
中域がしっかりと出るカッティング音が、リズムにしっかり馴染みます。 - ポップスやオルタナ系にもなじみやすい
明るく素直なトーンがボーカルや他の楽器と調和しやすいです。 - インディーロックでも多く使われている
軽やかでヌケの良い音が、バンドサウンドに抜け感を加えてくれます。 - クラシックロックの象徴的存在
ジミ・ヘンドリックスやクラプトンの例に見るように、60〜70年代ロックに不可欠な存在です。
ストラトキャスターはその設計上、音の立ち上がりが速く、コード感の輪郭がはっきり出るため、バンドサウンドに埋もれにくいという利点があります。
結果として、メロディラインが引き立つジャンルで特に力を発揮します。激しい歪みが必要なジャンルには工夫が必要ですが、幅広い音楽に対応できる万能さは他のギターにはない強みです。
ストラトキャスター使用アーティスト別モデルと音の違い
ストラトキャスターは見た目が似ていても、実はモデルごとにサウンドの方向性が異なります。著名なギタリストたちは、自分のプレイスタイルや音楽性に合ったモデルを選び、個性的な音を作り上げています。ここでは代表的なアーティストとそのモデル、そして音の違いについて紹介します。
アーティスト別に見るモデルと音色の傾向
- エリック・クラプトン:シグネイチャーモデル(アクティブ回路)
ブースト付きの中域が豊かで、滑らかで太いトーンが得られます。 - ジョン・メイヤー:Silver Sky(ストラト風)
トラディショナルなストラトに近い設計で、柔らかくナチュラルな音が特徴です。 - イングヴェイ・マルムスティーン:スキャロップド指板モデル
繊細なビブラートやダイナミクス表現に優れた操作性を実現。ピッキングに対して音の反応が鋭く、表現力豊かな演奏に適しています。 - ジェフ・ベック:ハイパワーピックアップ搭載モデル
幅広い音作りが可能で、指弾きにも繊細に反応します。 - ジミ・ヘンドリックス:ヴィンテージスタイルモデル(逆ヘッド仕様)
高音が柔らかく、ウォームでサイケデリックなサウンドが出せます。
それぞれのギタリストが求めるサウンドに合わせて、微妙に仕様を変えたモデルを選んでいます。同じストラトキャスターでも、ボディ材やピックアップ、ネック形状によって音の傾向は大きく変わります。自分の好みや目指すサウンドに近いアーティストのモデルを参考にすることで、理想の音により近づけるでしょう

ストラトキャスター 音作り・機材セット紹介で音を再現
ストラトキャスターはプレイヤーの個性が色濃く出やすいギターです。しかし、理想の音を出すには適切な機材セットとセッティングが欠かせません。ここでは、代表的な音色を再現するための音作りと、それに必要な機材を紹介します。
基本のセッティングと機材の組み合わせ
- アンプはクリーン寄りを基準に選ぶ
フェンダー系アンプ(Twin Reverbなど)はストラトとの相性が良く、クリアで立ち上がりの早い音が得られます。 - エフェクターはシンプルな構成から始める
オーバードライブ、コーラス、ディレイなど、必要最低限のエフェクトでストラト本来の音を活かします。 - ピックアップポジションを活用する
リアで鋭さを、センターで抜け感を、フロントで甘さを出すなど、使い分けが大切です。 - ボリューム・トーン操作でニュアンスを出す
演奏中にトーンノブを絞ることで、丸みのある音やローファイな質感が得られます。
アーティスト別の音作り例
- ジョン・フルシアンテ:アンプ直結+軽いクランチ。アンプはMarshallまたはVox系を好む。
- エリック・クラプトン:中域が強調されたセッティング。ブースターやトレブルブーストを使用。
- ジミ・ヘンドリックス:ファズフェイスやワウを使ったサイケな歪み。アンプはクランクアップ必須。
ストラトキャスターの音作りは、ギター単体では完結しません。アンプとの組み合わせや演奏スタイルによって音の印象が大きく変わります。好みのギタリストの音に近づけるには、使用機材を調べてセッティングを真似してみることが、最初の近道になるでしょう。
ストラトキャスター 太い音を出すためのポイント
ストラトキャスターは「細い音」と言われがちですが、設定や弾き方によっては十分に太い音も出せます。ここでは、ストラトで芯のある太い音を出すための具体的な方法を解説します。
太さを出すためのテクニックと工夫
- フロントピックアップを使用する
温かく丸みのある音が出せるため、太さを出したい場合に最適です。 - アンプで中低域を強調する
EQ設定でBASSとMIDDLEをやや上げ、TREBLEを控えめにすることで厚みが増します。 - ゲインは上げすぎず、適度なクランチに
音の輪郭が潰れない範囲で歪ませると、芯のある太さが出しやすくなります。 - 指弾きや重めのピッキングでアタックを意識する
アタック感があることで、実際以上に太く聞こえる効果が生まれます。 - コンプレッサーで音の密度を整える
音の強弱を揃え、存在感のあるトーンが得られます。
多くの人が「ストラトは細い」と感じる原因は、セッティングや奏法の選択にあります。正しく調整すれば、テレキャスターやレスポールに負けないくらいパワフルな音も出せます。フロントピックアップを起点に、アンプとピッキングの工夫を加えることで、太くて芯のあるサウンドを手に入れることができるでしょう。
ストラトキャスター 歪みサウンドを作るには?
ストラトキャスターはクリーンなイメージが強いかもしれませんが、適切なセッティングをすれば歪んだロックやハードなサウンドにも十分対応できます。ここでは、ストラトでしっかりと歪みを出すためのポイントを解説します。
歪みサウンドに向けた具体的な工夫
- ピックアップの選択が重要
リアピックアップは歪ませたときに輪郭がはっきりしやすく、パワフルな音に仕上がります。 - ブースターやオーバードライブを活用する
ゲインブーストにより、シングルコイル特有の細さを補いながら力強さを加えることができます。 - ミッドを強調するアンプ設定を意識する
中域が足りないと、音が軽く聞こえるため、ミドルを少し強めに設定するのが効果的です。 - ストラト特有のノイズに配慮する
シングルコイルはハムノイズが出やすいため、ノイズゲートやノイズレスPUへの交換も検討しましょう。 - 歪みエフェクトは段階的に重ねる
オーバードライブ→ディストーションと段階的に積むと、潰れにくい歪みが作れます。
ストラトキャスターで歪みを出すには、機材の選定とセッティングの工夫が重要です。シングルコイルならではの抜けの良さを活かしながら、歪みの芯をしっかり作りこめば、ロックやメタルでも力を発揮できます。ストラトならではの鋭さを武器に、個性的な歪みサウンドを楽しんでください。

ストラトキャスター 万能ギターと呼ばれる理由
ストラトキャスターは「万能ギター」と称されることが多いですが、その理由はどこにあるのでしょうか。幅広いジャンルに対応できる柔軟性や、演奏性・音作りの自由度が高いことがその背景にあります。ここではその具体的な根拠を整理します。
万能と呼ばれる理由のポイント
- ピックアップが3つあり音のバリエーションが豊富
リア・センター・フロントそれぞれに個性があり、切り替えるだけで全く違うトーンが得られます。 - ジャンルを選ばない対応力
ブルース・ロック・ファンク・ポップス・ジャズ・インディーと、幅広い音楽スタイルで使われています。 - 操作性に優れたコントロールノブ
ボリュームとトーンのノブにより、プレイ中でも柔軟に音を変化させることが可能です。 - 構造がシンプルでカスタマイズ性が高い
ピックアップやブリッジなどの交換がしやすく、プレイヤーのスタイルに合わせて調整できます。 - 演奏性が高く初心者にも扱いやすい
ネックが細めで軽量なため、長時間の演奏でも疲れにくい仕様です。
ストラトキャスターは、その柔軟な設計と多彩な音作りの幅によって、あらゆるプレイヤーの要望に応えてきました。ひとつのギターで複数のジャンルに対応できる点は、初心者にとっても安心材料となります。どんな演奏スタイルにも順応できるストラトは、まさに「万能」という言葉がふさわしいギターです。

ストラトキャスター テレキャスター どっちが自分に合う?
ストラトキャスターとテレキャスターは、どちらもフェンダー社が生んだ名機として知られています。しかし、そのサウンドや構造には大きな違いがあり、自分に合ったギターを選ぶには特徴をしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、両者の違いを比較しながら、選び方のヒントを紹介します。
サウンドの違いを比較する
- ストラトキャスターは柔軟で多彩な音色が魅力
3つのピックアップと5Wayセレクターにより、クリアなカッティングから滑らかなソロまで幅広く対応。 - テレキャスターは鋭く輪郭のある音が特徴
リアピックアップのジャキッとしたサウンドは、カントリーやロックンロールと好相性です。
構造と操作性の違い
- ストラトはトレモロユニット搭載で音の表現に幅が出せる
アーミングが可能で、滑らかなビブラートや効果音的な演奏が可能。 - テレキャスターは構造がシンプルでメンテナンスしやすい
初心者でも扱いやすく、パーツの交換や調整も簡単です。 - ストラトは曲線的なボディで抱えやすい
コンター加工が施されており、座っても立っても弾きやすい設計。 - テレキャスターは直線的なデザインで音がダイレクトに出る
無駄な要素がなく、ギターの鳴りそのものを楽しめます。
こんな人にはストラト/テレキャス
- ストラトキャスターが合う人
- 幅広いジャンルに挑戦したい
- 音作りにこだわりたい
- フェイザーやワウなどの空間系エフェクトをよく使う
- テレキャスターが合う人
- シンプルな構造で長く使いたい
- ロックンロールやパンクが好き
- 中低域がはっきりした音を求めている
ストラトキャスターとテレキャスターは、どちらも完成度の高いギターです。プレイスタイルや求める音、使うジャンルによって選ぶべきモデルは変わります。最終的には実際に弾いてみることが一番の判断材料ですが、特徴を知っておくだけでも選択に迷わず進めるはずです。自分の音楽性に合う1本を見つけましょう。

初心者に最適なストラトキャスターの選び方
ストラトキャスターは、多彩なサウンドと扱いやすい構造が特徴で、初心者にも人気の高いエレキギターです。しかし種類が豊富なため、初めての一本としてどのモデルを選べばよいのか迷う方も多いでしょう。ここでは、ストラトキャスターの中から初心者が失敗せずに選ぶためのポイントをわかりやすく解説します。
モデルは「Squier by Fender」シリーズから選ぶ
- Bullet Stratはコストパフォーマンスが高い
入門価格帯で品質も安定しており、まず1本目として選ばれています。 - Affinity Stratはやや上位で作りがしっかりしている
多少の余裕があればこちらがおすすめ。ネックや塗装の仕上がりも良好です。 - Classic Vibeシリーズは本格派の入り口
予算に余裕がある初心者向け。音質やパーツが上位モデルに近く長く使えます。
音作りを意識するならピックアップ構成をチェック
- SSS構成はストラトらしいクリーンな音が出せる
ジャンル問わず扱いやすく、基本的なサウンドを学ぶのに最適です。 - HSS構成はロック寄りで太い音が出る
リアにハムバッカーが搭載されており、歪ませたサウンドに強みがあります。
ボディ材と重量も選定基準に
- バスウッドやアルダー材は軽くて初心者に扱いやすい
ストラトキャスターの標準的な素材で、クセのない音が出ます。 - ボディが軽いモデルは練習時の疲労が少ない
長時間の練習でも集中力を保ちやすくなります。
最後は「好きな見た目」で決めるのも大切
- デザインやカラーで気分が上がることも重要なポイント
練習のモチベーションが上がるギターは、上達のスピードにも影響します。
ストラトキャスターは、初心者にも手が届く価格帯で多くのバリエーションが用意されています。予算に応じてモデルを絞り、音の好みや重量感、見た目の好みなどを考慮して選ぶと失敗しにくくなります。入門用とはいえ、自分が好きになれる1本を選ぶことが、長くギターを続けるための第一歩です。
初心者必見!ストラトキャスター使用アーティストと選び方ガイドの総括
ストラトキャスターは、数多くの名ギタリストに愛され、その音と操作性によって時代を超えて使われ続けているエレキギターの代表格です。音色のバリエーションやコントロールのしやすさ、演奏性の高さにより、幅広いジャンルで活躍するアーティストたちの表現を支えてきました。
その代表格とも言えるのが、エリック・クラプトンです。クラプトンの演奏スタイルは、過度な技巧や派手さではなく、音の質感やフレーズの間にこだわった洗練されたプレイに特徴があります。ストラトキャスターを通して紡がれる彼のサウンドは、今もなお「現代ギタープレイのスタンダード」として、多くのプレイヤーの参考となっています。クラプトンが提示したトーンと演奏美学は、ロックやブルースに限らず、ストラトの可能性を最大限に引き出す手本とも言えるでしょう。
一方、イングヴェイ・マルムスティーンのようなテクニカルな速弾きとクラシカルな旋律を組み合わせたプレイヤーは、ストラトの反応の良さを武器に独自の世界を構築しています。彼のシグネイチャーモデルには、速さ・明瞭さ・音抜けといった要素が備わっており、ハードロックやメタルに挑戦するプレイヤーにとって理想的な選択肢となっています。
ジョン・フルシアンテのように、音数を減らし「間」で聴かせるプレイヤーも、ストラトキャスターの自然なトーンを最大限に活かしています。アナログ機材を使い、感情を音に乗せるそのスタイルは、テクニック偏重ではないストラトの新しい可能性を示しています。ジミ・ヘンドリックスがかつて見せた表現力の限界を押し広げるような演奏も、現在までストラトキャスターの多様性と自由度を象徴し続けています。
加えて、ストラトキャスターはポップス、ファンク、R&B、インディーロックなどの現代的なサウンドにもマッチし、ジョン・メイヤーやジェフ・ベック、マーク・ノップラーといったアーティストたちが、それぞれのジャンルで独自のサウンドを構築しています。国内では、Charや山内総一郎、SUGIZOといったプレイヤーが、それぞれの音楽性に合わせてストラトを選び、日本独自のプレイスタイルを形成しています。
ストラトキャスターの特徴は、プレイヤーの意図を音に反映させやすい点にあります。ピックアップの切り替えやトーン操作で音のニュアンスを細かく調整できるため、ジャンルを問わず自分だけのサウンドを追求することが可能です。パンクやメタルといった激しいジャンルでも、改造やセッティング次第で力強く対応できる柔軟性を持ち合わせています。
初心者向けの視点でも、演奏性の高さや豊富なモデルラインナップ、選択肢の広さから、ストラトキャスターは非常に優れた一本です。特に「どんなジャンルを弾くか決まっていないけれど、色々試したい」というプレイヤーにとっては、最初のギターとして非常に理にかなった存在と言えるでしょう。
ストラトキャスターを使用しているアーティストたちのスタイルと音作りに触れることで、ギターの選び方や自分の目指す方向性がより明確になります。ギター選びで迷ったときこそ、アーティストのプレイに耳を傾け、その音と向き合ってみてください。それが、最適なストラトキャスターとの出会いに繋がるはずです。




コメント