初めてのエレキギターを選ぶとき「音はどう?」「弾きやすい?」「長く使える?」と疑問が尽きないものです。そんな中で候補に挙がることが多いのがヤマハ パシフィカ112V。価格帯以上の実力を持つと評判ですが、レビューを深掘りすると良い評価ばかりではなく注意点も見えてきます。
この記事ではヤマハ パシフィカ112Vの評価を軸に、実際の使用感やレビューの背景を丁寧に整理します。さらに、シリーズ内のモデル比較や演奏に影響する仕様の違いも解説し、失敗しない選び方のヒントを提供します。
これからギターを始めたい方、買い替えを検討している方の判断材料になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。
出典:ヤマハ公式
- 良い評価と悪い評価の理由や背景
- 中古購入のメリットとリスク
- 100シリーズ各モデルとの違い
- トレモロアームや指板材による演奏性の違い
ヤマハ パシフィカ112Vの評価・評判や実力を徹底解説
この章では、ヤマハ パシフィカ112Vの評価をわかりやすく整理しています。レビューの中から良い意見と気になる意見をそれぞれ取り上げ、その理由をていねいに確認しながら、最終的にどんな結論になるのかをまとめました。
初めてギターを選ぶ方が「本当に自分に合うのか」「後で失敗したと思わないか」といった不安を解消できるよう、実際の弾き心地やモデルごとの選び方のポイントも交えて解説しています。

ヤマハ パシフィカ112Vの評価とレビューを総括して解説
シリーズの中核を担う112系は、アルダーボディと標準ロングスケール、SSH+コイルタップという可変性を組み合わせ、練習から小規模ライブのサブ機まで幅広く使われています。
アルダー無垢は同価格帯に見られる合板と比べて共振の乱れが少なく、特にクリーン〜軽いクランチで分離が明瞭になりやすい設計です。
指板R350の22フレット、薄めのC寄りグリップは一般的なセットアップ値(例:12Fで1.6〜2.0mm)に素直に追従し、基礎整備の学習にも向きます。
良いレビューの要点を解説
多くのユーザーからは、価格帯以上の完成度や扱いやすさが支持されています。具体的には以下のような声が目立ちます。
- クリーンから軽いクランチでの音抜けと分離感が明瞭
- SSH+コイルタップで幅広い音色に素早くアクセスできる
- 薄めのCシェイプネックとR350指板で押さえやすく演奏が快適
- 弦高やオクターブ調整が素直に決まり、入門者でも整備しやすい
こうした評価が得られる背景には、アルダー無垢ボディとアルニコVピックアップの組み合わせによる安定した倍音構成があります。
また、5Wayセレクターとコイルタップ機能によって、シングルとハムの使い分けをスムーズに行える点も好評です。
さらに、標準的なスケールやフレット数、ヴィンテージタイプのトレモロを備えているため、教則本どおりの数値設定に合わせやすく、再現性の高いコンディションを保ちやすいことが初心者の安心感につながっています。
良い評価のレビュー内容を検証!
パシフィカ112Vが高く評価されるのは、価格帯を超えた設計上の工夫と実用性が理由です。とくに次のような要素が挙げられます。
- アルダー無垢ボディとアルニコVピックアップの組み合わせにより、過度なピークが抑えられ、倍音のバランスが整いやすい
- 5Wayセレクターとコイルタップの役割分担が明確で、場面に応じた音色を素早く切り替えられる
- リアハムはリード演奏で芯のあるサウンド
- コイルタップONはコードの分離感を重視
- 2番・4番ポジションは位相感のあるカッティングに適する
さらに、ヴィンテージタイプのトレモロと22フレットの標準設計は、教則本で紹介される弦高やオクターブ調整値に素直に追従します。そのため、初心者でも再現性の高いコンディションを作りやすく、練習効率の向上やモチベーション維持につながる点が支持の背景となっています。
悪いレビューの要点を解説
一部のユーザーからは、次のような指摘が挙がっています。
- 強い歪みをかけた際に高域がザラついて耳につきやすい
- 低域の押し出しがやや控えめで厚みに欠ける印象を受ける
- トレモロアームを多用するとチューニングが動きやすい
これらの意見は、単体で見れば致命的な欠点というよりも、上位機種(611や612シリーズ)との直接比較で際立ちやすいポイントです。
上位モデルはピックアップやブリッジ、ロック式ペグなどのグレードが上がるため、音の密度やチューニング安定性で優位に立ちます。その結果、112Vの特性が「弱点」として認識されやすいのです。
悪い評価のレビュー内容を検証!
悪いレビューの多くは「上位機種との比較」と「運用条件」に起因します。112V自体の基本性能は入門機として十分ですが、特定の環境では差が浮き彫りになりやすいのです。
主な要因を整理すると以下のとおりです。
- 高ゲイン環境では、ピックアップやブリッジ、ペグ、ナット、電装部品のグレード差が音に出やすく、上位機種は倍音のきめ細かさやサスティンの厚みで優位に立ちます
- EQ設定でプレゼンスを強調しすぎたり、ピックアップ高を上げすぎたりすると、高域の粗さが強調されやすくなります
- 弦の劣化や強めのピッキングも、低域の押し出し不足や音像の荒れにつながります
- ヴィンテージタイプの6点支持トレモロは、構造上アーミングで張力が動きやすく、戻りが安定しにくい場合があります
- ナット溝の潤滑不足やスプリング・クローの調整不足があると、チューニングの動きが顕著になります
このように、悪い評価の背景には「上位機との差」と「セッティングの影響」が重なっています。適切なEQ調整やメンテナンスを行えば、多くの不満は軽減できるため、必ずしもギターそのものの欠点とは言い切れません。
ヤマハ パシフィカ112Vの評価とレビューを総括して解説の総括
ヤマハ パシフィカ112Vは、入門機として求められる「学習効率」と「再現性」の両面で優れており、価格に対して装備と完成度のバランスが取れています。多くの好意的なレビューは、設計の素直さと調整のしやすさに支えられており、安心して最初の一本として選べる理由となっています。
一方で、否定的な声の多くは112Vそのものの欠陥ではなく、以下のような条件で表れやすいものです。
- 上位機種(611/612系など)との相対比較による差
- 高ゲイン環境での高域の粗さや低域の物足りなさ
- トレモロの使用頻度や調整不足によるチューニング変動
これらは設定やメンテナンスである程度補える要素であり、必ずしも致命的な弱点ではありません。
総合的に見ると、112Vは「初めての一本」として選んでも後悔の少ないモデルです。
- アーム表現を取り入れたいなら112Vを基準に選択
- チューニング安定性を優先するなら120Hを検討
- さらなる密度感や上質な音を求めるなら611/612系へステップアップ
用途やプレイスタイルに応じてモデルを選び分けることで、納得感の高い選択につながります。

主要スペック(公式カタログ準拠の要約)
| 項目 | PACIFICA112V(公式値) |
|---|---|
| スケール | 648mm |
| 指板R | 350R |
| フレット数 | 22 |
| ボディ | アルダー |
| ネック | メイプル(ボルトオン) |
| 指板 | ローズウッド(112VM/VMXはメイプル) |
| ブリッジ | ヴィンテージタイプ(ブロックサドル) |
| ピックアップ | S(アルニコV)×2、H(アルニコV)×1 |
| コントロール | Vol、Tone(コイルタップ)、5Way |

ヤマハ パシフィカシリーズの評判は?
パシフィカシリーズ全体は、入門者から中級者まで幅広い層に安定した支持を得ています。その理由は大きく分けて以下の点にあります。
- 価格に対する性能のバランスが優れており、コストパフォーマンスが高い
- 製造精度のバラつきが少なく、個体差による当たり外れが少ない
- 国内外での入手性が高く、サポート体制も整っている
とくにパシフィカ112Vは、コイルタップによる音色の広さや、ブロックサドル採用によるサスティン確保が評価されており、練習から小規模ライブへの移行をスムーズにする存在です。
また、同一価格帯で複数の派生モデル(112VM、VMX、112JL、120Hなど)が展開されているのも特徴です。これにより、演奏スタイルや手の大きさ、デザインの好みに合わせて選べる柔軟性があります。こうしたラインアップはユーザーにとって選択の幅を広げ、満足度を高める要因となっています。
一方で、よく話題になるのは上位機種との比較です。
- 歪みを深くかけた際の倍音のきめ細かさ
- 低域の押し出しや厚み
これらは、ピックアップの磁力設計や巻き数、ブリッジやナットの材質、ペグの保持力、配線材やポットの品質など、複数要素が影響する部分です。上位モデルの611や612シリーズではこの領域により多くのコストが投じられており、違いが感じられやすい傾向にあります。
ただし、練習や小規模アンプでの演奏では、アンプのプレゼンスやトレブル、ミッドの調整、EQ前段にコンプレッサーやトレブルカットを導入することで十分に補正可能です。
こうした「必要十分な土台」と「拡張余地の広さ」が、シリーズ全体の評判を押し上げていると言えます。
さらに、ヤマハ公式カタログには派生モデル間の仕様表が掲載されており、スペックの違いが明確に比較できる点も安心材料です(出典:ヤマハ公式カタログPDF)
加えて、楽器店大賞2023の受賞実績もあり、コスト重視の初心者層だけでなく、セカンドギターや改造ベースを探す層からも継続的に選ばれています(出典:PR TIMES ヤマハ公式リリース、Musicman)。

ヤマハ パシフィカ112Vの音が悪いという意見を検証する
パシフィカ112Vに対して「音が悪い」と指摘されることがありますが、その多くは特定の条件下に限られます。特に目立つのは、強い歪みをかけたときに高域がザラついて聞こえるケースです。
このモデルはアルニコVマグネットを採用したSSH配列とコイルタップ機能を備えており、クリーンからクランチにかけては透き通ったアタックと音抜けの良さを示す設計です
しかし、上位モデルである611や612シリーズでは、ブリッジやペグ、ナット、電装系にグレードの高い部品が搭載されています。そのため、倍音の整い方やサスティンの密度で差が生じ、比較すると112Vの高域が荒く感じられることがあるのです。
一方で、この弱点はセッティング次第で大きく緩和できます。具体的な調整方法としては以下のような手順が有効です。
- アンプのプレゼンスやトレブルを少し控えめにする
- ハイゲイン時にはミドルを適度に持ち上げてバランスを整える
- コンプレッサーを加えてアタックの尖りを滑らかにする
- リアピックアップをコイルタップして帯域を軽くし、荒さを抑える
なお、112Vのコイルタップはトーンノブのプッシュプルで操作でき、5ウェイセレクターの2番ポジションでは自動的にリアがタップされる仕様になっています(出典:ヤマハ公式 FAQ コイルタップの動作)
こうした点を踏まえると、「音が悪い」という評価はギター本体の欠点というよりも、使用するゲイン量やEQ設定、さらにはピッキングの強さといった運用条件に左右されやすいと言えます。基礎性能の範囲内で十分に解決可能な問題であり、適切に調整すれば多くのシーンで快適に活用できるモデルです。
ヤマハ パシフィカ112Vの基本セッティングの方法(使い方)
パシフィカ112Vは、操作系や構造がシンプルで、初心者でも扱いやすいよう設計されています。基礎練習から小規模な現場まで対応できるため、最初に手にするエレキギターとして安心感があります。
まずは操作系から整理してみましょう。
- 5ウェイセレクターで、ネック、ネック+ミドル、ミドル、ミドル+リア(自動タップ)、リア(H/タップ切替)の音色を選択可能
- トーンノブのプッシュプルでリアをコイルタップでき、シングル相当の軽やかな帯域に切り替え可能
- クリーンから歪みまで、幅広いジャンルの音作りを効率的にカバーできる
(出典:ヤマハ公式 PACIFICA 100シリーズ紹介、FAQ)
トレモロは6点支持のヴィンテージタイプでブロックサドルを採用しています。アームはねじ込み式で、装着時には角度をつけずまっすぐ挿入し、必要以上に締め込まないことが推奨されています。
- 激しいアーミングはチューニング変動を招きやすいため、初期段階では浅めの動作から慣れる
- アームを使わない場合は、スプリング本数やクロー位置を調整し、ブリッジをベタ付け寄りにすることで実質固定化できる
続いてメンテナンス面です。ギターを快適に保つためには、以下の基本を押さえておくと安心です。
- 弦交換、チューニング、弦高・オクターブ調整、ネック反りの確認が基本
- トラスロッドはヘッド側からアクセス可能で、適合レンチで少しずつ調整
- ローズウッド指板は乾燥時期にオイルケアを行い、ひび割れ防止に活用
- メイプル指板は塗装仕上げのため、乾拭き中心で清潔に保つのが無難
数値の目安としては、入門時は12フレットで6弦側が約2.0mm、1弦側が約1.6mm程度から調整すると扱いやすく、ビビりと弾きやすさのバランスを取りやすいです。これらはあくまで基準であり、演奏スタイルに応じて調整すると最適化できます。
公式のスペック表や取扱説明資料を併読すると、セッティング手順をより理解しやすくなります(出典:ヤマハ公式 製品仕様ページ)。
初心者におすすめ!パシフィカ112Vセットの紹介
パシフィカ112Vは扱いやすさと音作りの幅広さで初心者に支持されているモデルですが、さらに効率よく練習を始めたい人には「初心者セット」での購入が有効です。本体に加えて周辺機材が一括で揃うため、購入したその日から練習を始められるのが最大のメリットです。
初心者セットに含まれる内容は以下の通りです。
- ギター本体(パシフィカ112V)
- ミニアンプまたはヘッドホンアンプ
- チューナー、ストラップ、シールド
- スタンド、ピック、ソフトケース
- 予備弦や簡易教則本、クリーニング用品など
特にアンプの種類は、練習の質を左右する重要な要素です。
- ミニアンプはスピーカーから音を出すため、音作りや空気感を体感しながら学べる
- ヘッドホンアンプは深夜や集合住宅でも迷惑をかけずに練習でき、時間に縛られず継続しやすい
代表的なセットを整理すると以下のようになります。
| セット種別 | 主な構成内容 | 想定用途 | 検討ポイント |
|---|---|---|---|
| ベーシック9点 | 本体、ミニアンプ、チューナー、ストラップ、シールド、スタンド、ピック、ケース、予備弦 | 通常の自宅練習 | ミニアンプの出力と簡易EQの有無 |
| サイレント重視 | 本体、ヘッドホンアンプ、チューナー、他小物一式 | 深夜や集合住宅 | AUX INやエフェクト搭載の有無 |
| 充実14点 | 本体、上位小型アンプ、教則、クリーニング用品、他小物追加 | 長期的な基礎強化 | アンプのゲイン構造と外部入力対応 |
このセットをおすすめする理由は下記の通りです
- 最低限必要な機材が揃うため、追加購入の手間が省ける
- チューナーやケースが含まれ、日常のメンテナンスや持ち運びがスムーズになる
- アンプを通した本格的な音作りや、静音環境での集中練習など、環境に合った学習が可能になる
- 教則や練習補助アイテムが含まれることで、基礎から効率的にステップアップできる
- 全体を一括で揃えることでコストを抑え、練習に集中できる
つまり、パシフィカ112Vの初心者セットは「無駄なく、安心して、継続的にギターを学べる環境」を整えるためのパッケージです。最初の一歩をスムーズに踏み出すために、単体購入よりもセット購入を検討する価値は大きいと言えるでしょう。
ヤマハ パシフィカ112Vの選びかたを徹底解説!
ヤマハ パシフィカ112Vを中心に、中古での選び方や100シリーズのモデルごとの特徴、トレモロアームの有無による演奏の違い、さらには指板材の選び方までを分かりやすく整理しました。
これからエレキギターを始める人が「どのモデルを選べばいいのか」と迷ったときに、疑問を解消して安心して選べるようにまとめています。

ヤマハ パシフィカ112Vの中古は初心者におすすめできるか?
中古市場にも多く流通しているパシフィカ112Vですが、初心者にとっては必ずしも最適な選択とは言えません。その理由を整理してみましょう。
中古購入で注意すべき点
中古のギターは一見価格が安く魅力的に見えますが、以下のような点を自分で判断できるかが大きな分かれ目です。
- 新品との価格差が小さい
パシフィカ112Vは新品価格自体が手頃なため、中古との価格差が1万円前後しかない場合が多いです。保証や初期不良対応が付く新品の方が安心感が大きく、中古を選ぶ金銭的メリットは小さくなります。 - 現物の状態確認が難しい
ネックの反りやねじれ、トラスロッドの効き、フレットの摩耗、電装のガリや接触不良などを見抜けなければ、購入後に追加の修理費用が発生する可能性があります。 - トレモロや金属部品の劣化
6点支持トレモロのサドルやイナーシャブロックはサビや固着が起きやすく、調整幅が限られると正しいセッティングが難しくなります。 - 付属品の欠品リスク
純正アームや六角レンチ、ギグバッグが欠けている場合、別途購入が必要です。小さな出費でも積み重なると新品との差が縮まります。
初心者におすすめしにくい理由
初心者にとって中古を選ぶ難しさは「状態を見極める知識」と「整備の手間」が必要になることです。状態が悪い個体を選んでしまうと、練習以前に調整や修理に時間と費用を取られてしまい、学習のモチベーションを下げる要因になりかねません。
さらに、新品と中古の価格差が思ったほど大きくないため、保証や初期不良対応がある新品を選んだ方が安心感と費用対効果の両面で優れています。
総括してまとめると
- 初心者にとっては、状態確認や整備に不慣れなうえ、新品との差額が小さいためメリットが薄い
- どうしても中古を検討するなら、楽器店の保証付き整備済み品を選ぶのが安全
上記の理由から、初心者には中古よりも新品のパシフィカ112Vを選ぶ方が安心で、効率よく練習を始められるでしょう。

ヤマハ パシフィカ100シリーズの比較を解説
100シリーズは入門価格帯ながら装備差で目的別に最適化されています。仕様差を押さえると選択が明確になります。
| 型番 | 配列・機能 | 指板 | ブリッジ | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| PAC112V | SSH+コイルタップ | ローズウッド | 6点支持トレモロ | 最も万能な基準機 |
| PAC112VM | 112Vの指板違い | メイプル | 6点支持トレモロ | 明るいアタックと外観差 |
| PAC120H | HH(コイルタップ有) | ローズ系 | 固定ブリッジ | チューニング保持と太い歪み |
| PAC012 | SSH(タップ無) | ローズ/代替材 | 6点支持トレモロ | 価格最重視の入門用 |
100シリーズは入門価格帯ながら装備や仕様に違いがあり、用途や好みに合わせて最適なモデルを選びやすい構成です。モデルごとの特徴を整理すると判断がスムーズになります。
PAC112V:最も万能な基準機
- 配列・機能:SSH+コイルタップ
- 指板:ローズウッド
- ブリッジ:6点支持トレモロ
112Vはシリーズの基準機として位置づけられています。クリーンでは分離感が高く、クランチや歪みでは芯をしっかり残せるのが強みです。コイルタップを備えることで幅広い音作りが可能になり、最初の一本として後悔が少ない選択肢です。
PAC112VM:メイプル指板による明るいキャラクター
- 配列・機能:SSH+コイルタップ
- 指板:メイプル
- ブリッジ:6点支持トレモロ
112Vとの違いは指板材にあります。メイプル特有の立ち上がりの速さや明るいアタック感が得られるため、カッティング主体のプレイや明るい外観を好む人に適しています。音色面でも軽快さが加わるのが特徴です。
PAC120H:固定ブリッジで安定感を重視
- 配列・機能:HH(コイルタップ有)
- 指板:ローズ系
- ブリッジ:固定ブリッジ
固定ブリッジを採用することでチューニングの安定性が高く、サスティンの太さも得られます。強いゲインを多用するジャンルや、ドロップチューニングで演奏する場面に向いています。トレモロ操作を必要としないプレイヤーにおすすめです。
PAC012:価格最優先の入門用
- 配列・機能:SSH(コイルタップ無)
- 指板:ローズウッドまたは代替材
- ブリッジ:6点支持トレモロ
012はシリーズの中で最も低価格のモデルです。音作りの可変性は112系に及ばないものの、ギターを始めてみたいという段階で費用を抑えたい人に適します。ただし長期的に使うことを考えると、少し上位の112Vを選んだ方が拡張性や満足度は高くなります。
ヤマハ パシフィカ100シリーズの比較を解説のまとめ
- 用途が定まらない段階では、バランスに優れた112Vを起点にするのが無難
- アーム操作を必要としないなら、固定ブリッジの120Hが安定性で優位
- 音の立ち上がりや外観の明るさを求めるなら112VM
- 予算を最優先するなら012が候補だが、長期的には112Vが安心
各仕様の詳細は、ヤマハ公式の製品ページや統合スペックPDFで確認できます(出典:PAC100シリーズ紹介、統合PDF)。
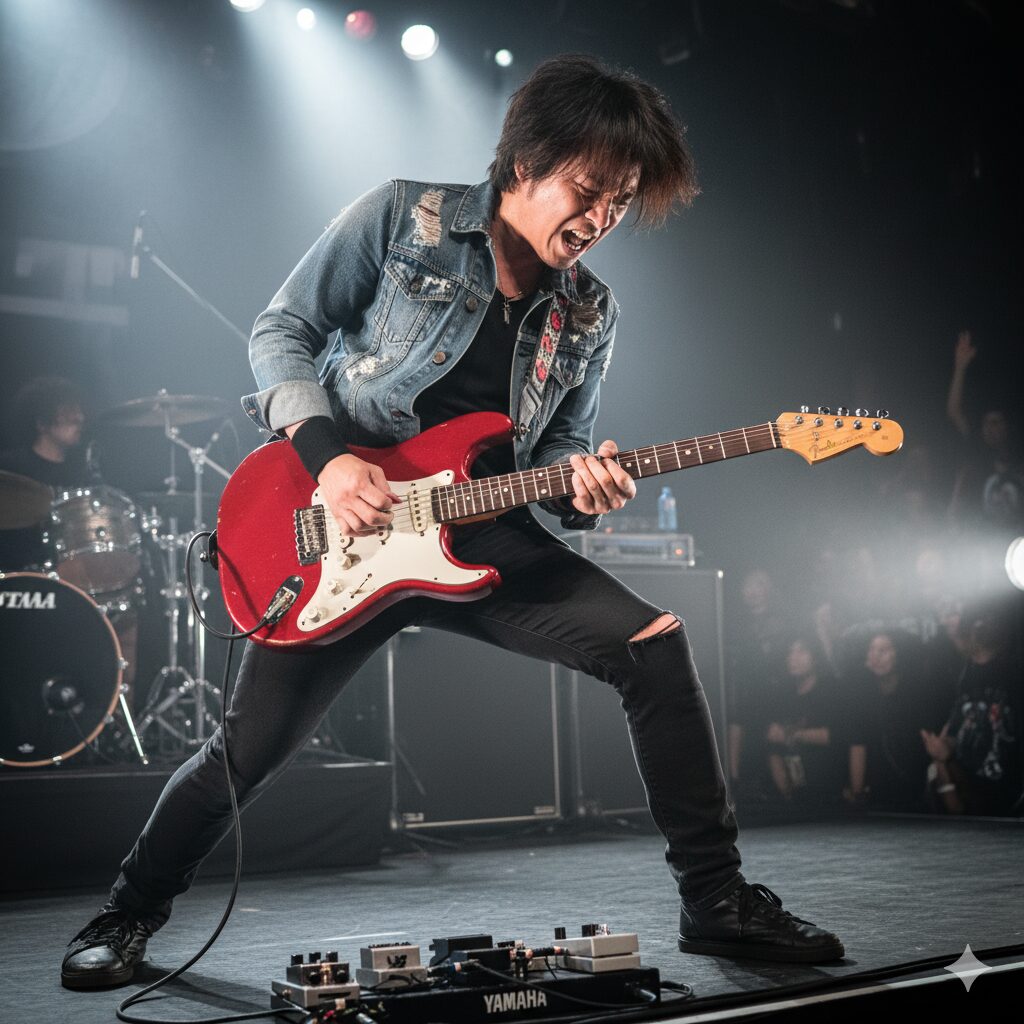
トレモロアームの有無で演奏にどんない違いがでるの?
エレキギターにおけるトレモロアームは、音の表情をコントロールできる装備の一つです。初心者にとっては「必要なのかどうか」が判断しにくい部分ですが、代表的なプレイ例を知ると理解が深まります。
トレモロアームが生み出す表現力
トレモロアームを搭載すると、次のような表現が可能になります。
- ゆるやかなビブラートで音に揺らぎを加える
- コードをまとめて揺らし、広がり感を演出する
- ハーフトーンでのきらめきや透明感を強調する
このように、アームを少し触るだけでも、音楽の雰囲気がガラリと変わります。
有名ギタリストのアーム活用例
- ジミ・ヘンドリックス:大胆なアーム操作で音程を大きく変化させ、サイケデリックでトリッキーな表現を実現
- ジョン・フルシアンテ(Red Hot Chili Peppers):白いジミヘン」と評され、大きなアーミングや微妙な揺らしでシンプルなフレーズに情緒を加える、まさにアーミングの手本。
このように使い方次第で、派手な演出から繊細なニュアンスづけまで幅広い表現に活かせます。
トレモロ搭載モデルと固定ブリッジモデルの違い
- PAC112V / PAC112VM(6点支持トレモロ搭載)
セッティング次第で可動域と戻りのバランスを調整可能。表現の幅を広げたい人に向いています。 - PAC120H(固定ブリッジ)
弦の張力が一定で、チューニングの安定性やサスティンの密度に強みがあります。深い歪みや低音弦を使う演奏で特に有利です。
(出典:ヤマハ公式 PAC100シリーズ紹介、統合スペックPDF)
初心者にとっての判断基準
- アームを積極的に使ってみたいなら、まずは112Vを選んで幅広い表現を体験してみる
- アームを使わない期間は、スプリングとクローを調整してブリッジをベタ付け寄りにすれば、安定した運用も可能
- 安定性や調整の手間を最優先するなら、最初から固定ブリッジの120Hを選んで練習に集中するのも良い選択
トレモロアームの有無で演奏にどんない違いがでるの?のまとめ
初心者にとってトレモロの有無は迷いやすいポイントですが、「表現の幅を体験したいか」「安定を重視したいか」で決めると分かりやすくなります。特に112Vは柔軟に運用できるため、最初の一本として学習効率を高めやすいモデルと言えるでしょう。
指板材の違いで演奏にどんな違いがでるの?(ローズウッド/メイプル/ウォルナット)
ギターの指板材は、音色のニュアンスだけでなく、手触りやメンテナンスのしやすさにも直結します。パシフィカ100シリーズではローズウッド、メイプル、ウォルナットといった選択肢があり、それぞれに特徴があります。
ローズウッド指板
- 表面は未塗装が一般的で、木地に近い自然な手触り
- 汗を吸いやすく、滑りにくい感覚で演奏できる
- 高音域がやや落ち着き、コード主体のプレイでまとまりを感じやすい
- 乾燥時期には軽いオイルケアを行うのが一般的なメンテナンス方法
メイプル指板
- クリア塗装によりツルリとした感触で、立ち上がりが速いアタック感
- 明るい色味で、50〜60年代のクラシックなルックスを好む層に人気
- 長期使用後のフレット交換時には、塗装のタッチアップが必要になる場合がある
ウォルナット指板
- 色味や触感はローズウッドに近く、代替材として採用が進んでいる
- パシフィカでは112JLなどに採用されており、公式スペックにも明示
- 見た目はローズよりやや明るめで、落ち着いた雰囲気を持つ
初心者にとっての選び方
実際の音色への影響は、アンプ設定、ピックアップ、弦、ピッキングの方が大きく、指板材による違いは「微調整の範囲」にとどまることが多いです。したがって、初心者が重視すべきは以下のポイントです。
- 手触りの好み(滑らかな方が弾きやすいか、木地感が落ち着くか)
- 見た目の好み(ナチュラルかクラシックか)
- メンテナンスに手間をかけられるかどうか
ラインナップの設計もわかりやすく、112Vはローズウッド、112VM/VMXはメイプル、112JLはウォルナットと、好みに応じて選びやすい構成になっています。初心者でも、最初の一本から自分に合った感触を見つけやすいのがパシフィカシリーズの魅力です。

ヤマハ パシフィカ112Vの評価とレビュー総まとめ!良い点も悪い点も徹底検証の総括
ヤマハ パシフィカ112V 評価に関する情報を整理すると、本機は入門価格帯で扱いやすさと音作りの幅を両立し、初めての一本として安心して選びやすいモデルだと判断できます。
クリーンからクランチの明瞭さ、コイルタップを活かした可変性、標準的な設計に基づくセッティングのしやすさが強みで、否定的な評価の多くは上位機との比較条件や設定次第で緩和できます。
- クリーン〜軽いクランチでの抜けと分離が良好で、SSH+コイルタップにより音色範囲が広い
- 教則の標準値に合わせやすい設計で、弦高やオクターブ調整などの再現性が高い
- 強い歪みでの高域の粗さや低域の物足りなさは、EQやコイルタップ運用で改善しやすい
- トレモロを使うか迷う段階でも、可動域を抑えた運用や固定寄り設定で柔軟に対応可能
- 同価格帯の派生モデル(112VM、120H、012など)と比較しやすく、用途に応じた選択が取りやすい
以上を踏まえると、パシフィカ112Vは価格に対して装備と完成度のバランスが取れており、学習効率と扱いやすさを重視する人に適しています。
アーム表現を試したいなら112Vを起点に、安定重視なら固定ブリッジの上位・派生モデルを検討する流れが実用的で、総合評価としては購入候補に十分値すると言えます。




コメント